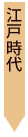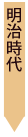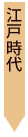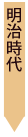| 1868(明治元) |
奈良奉行を廃し、興福寺をして
町政にあたらせ、ついで大和鎭撫
総督府、さらについで奈良府が
置かれる。 |
| 1869(明治2) |
奈良府を奈良県と改称。 |
| 1870(明治3) |
五条県設置。 |
| 1871(明治4) |
大和一国を所轄する奈良県を
設置。奈良・郡山など20カ所に
郵便役所・郵便取扱所を設置。 |
| 1972(明治5) |
県下最初の新聞「日新新聞」
発行される。 |
| 1973(明治6) |
奈良角振町に第一大屯所(警察署の
前身)設置。 |
| 1875(明治8) |
東大寺大仏殿回廊で第一次奈良
博覧会大会が開催される。 |
| 1876(明治9) |
奈良県を堺県に合併。 |
| 1879(明治12) |
郡山で第六十八国立銀行が開業。 |
| 1880(明治13) |
奈良公園が開設される。 |
| 1881(明治14) |
堺県が大阪府に合併、大和国も
大阪府の管轄となる。 |
| 1884(明治17) |
フェノロサ、政府の命により
大和国の古社寺を調査。 |
| 1887(明治20) |
奈良県を再設置。 |
| 1888(明治21) |
第1回県会が東大寺回廊で
始まる。 |
| 1889(明治22) |
十津川地域に大水害。罹災者、
北海道で移住。 |
| 1890(明治23) |
橿原神宮が創建される。 |
| 1892(明治25) |
奈良−大阪・湊町間に鉄道開通。 |
| 1895(明治28) |
帝国奈良博物館が開館。 |
| 1897(明治30) |
古社寺保存法により国宝60点、
特別保護建造物19棟指定。 |
| 1898(明治31) |
奈良町に県下最初の市制施行。 |
| 1899(明治32) |
関西鉄道株式会社により関西本線
が全通。 |
| 1908(明治41) |
奈良市内に電話開通。 |
| 1910(明治43) |
平城遷都1200年祭を施行。 |